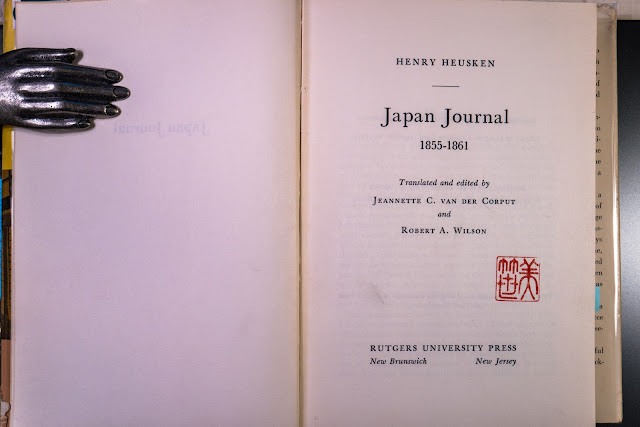「日英同盟の復活」がちょっとした話題になっている。去年の一月に日本とイギリスとの間で、日英防衛協力、次期戦闘機の共同開発などを盛り込んだ二国間協定が締結された。いわば新しい日英同盟だと言われている。イギリスはEU離脱で、「グローバル・ブリテン」をスローガンに、ヨーロッパよりも、経済発展著しいアジア(かつて植民地を持ち、宗主国として影響力を行使していた国々)にフォーカスを当て、インド、オーストラリア、ニュージーランド、カナダなど旧大英帝国構成国との連携を目指してしている。さらに日本をアライアンスパートナーに選び、ロシアの軍事的脅威、中国の海洋進出、台湾有事など、武力による現状変更の試みに対抗しよう。自由で開かれたインド太平洋地域の保証、専制的な独裁体制に対し、民主主義、法の支配、自由主義といった価値観を共有する国同士の連携をしようという戦略だ。一国二制度が反故にされ、香港の民主主義が危機的事態に陥っていることも影響している。一方でこれはアメリカの影響力の退潮の補完であるとも言える。広大なユーラシア大陸の東西両端に位置する島国同士が、再び新たなアライアンスを組む。「イギリスはヨーロッパの国ではないのか。なぜアジアに?」という疑問をよそに、欧亜の新たな枠組みを企図するイギリス。その意図と歴史的背景は何なのか。5年前に書いたブログも参照願いたい。2019年3月28日「イギリスはヨーロッパなのか?」
明治の日英同盟(1902年締結)の背景には、大英帝国にとっても、アジアの新興国日本にとっても、共通する仮想敵国ロシアの存在があった。ロシアは、黒海に軍港を確保しようとクリミア戦争を起こしたり、アジア太平洋に不凍港や鉄道を求め、満洲・朝鮮権益を獲得しようとしたり、いわゆる「南下政策」に躍起になっていた。この動きに対抗するために、それをユーラシア東西同盟で挟み撃ちにしようというわけだ。海洋国家イギリスには、伝統的にアジアへ進出する際の障壁としてヨーロッパの大陸国家の存在があった、それはかつての新興国イングランドにとってはイスパニア/ポルトガルでありフランスであり、近代の大英帝国においてはロシア、フランス、ドイツであった。一方の、開国まもない新興国家、日本にとって安全保障上の脅威、「一等国への道」に立ちはだかる脅威は、朝鮮、満洲を狙うロシアであった。日本はイギリス、アメリカを味方につける戦略をとり、それが功を奏して日露戦争に勝利できたわけだ。その後、日本は列強諸国に肩を並べてアジア植民地獲得競争に参入し、ついに日英は対立し戦争までしたのだが、今日的には、両国はそのロシアに加えて、中国を脅威と捉え、再び同盟を組もうというわけだ。ユーラシア大陸の内陸国家に対抗する、海洋国家のアライアンス。その戦略の妥当性、効果の議論は別にして、「脱亜入欧」の日本、「脱欧入亜」のイギリス。 このユーラシア大陸の東西両端に位置する島嶼国の動きにはどのような歴史的、地政学的な背景があるのだろう? 再び光が当たり始めた日英の関係強化の動きを機に考察してみた。
 |
| 「日英同盟」1902年 |
 |
| シンガポール陥落 1941年 |
 |
| 新たな「日英同盟」2023年1月 |
日英両国は、言うまでもないことだが、ヨーロッパとアジアという地理的に異なる位置にあり、異なる歴史を歩んできた。しかし、地球儀を俯瞰的に眺めてみると、両国にはユーラシア大陸の周辺部の島嶼国であるという地理的な立ち位置と、その条件に規定された地政学上の環境、歴史に共通する点がいくつかあることに気づくだろう。「地政学上の近似性」、「歴史の同期性」とでも言うものかもしれない。もちろん多くの相違点もあるが、その歴史を比較研究すると、いろいろ日本にとって示唆に富むヒントが見えてくる。
両国の成り立ちの歴史の共通点は
一言で言えば、大陸の先進文明、大陸の強大な帝国の影響下にあった辺境の島国が、王権を確立し国の形を作り、その文明、文化の影響下にあり、それを長きにわたって受容しながらも、強大な帝国の政治的、経済的、文化的なプレッシャーから離脱して独自の帝国を築いてゆく、という歴史ストーリーを共有している。
すなわち、日本は中国文明圏の国であり、現代に至るまで、文字として漢字を用い、儒教的道徳観を持ち、日常生活のあらゆる面で中国文明の影響を受けた国である。倭国時代には歴代中国王朝に朝貢し冊封を受けて王としての統治権威を保証された国(クニ)であった。しかし、やがて歴代中国王朝中心の華夷思想、朝貢冊封体制から離脱し、日本独自の「天下」を目指す歴史を歩むことになる。さらに時代が下ると、長い鎖国を解き、開国以後は、中国文明圏である東アジアにありながら西欧文明をいち早く取り入れ、「脱亜入欧」をスローガンに西欧流の近代化を果たし、欧米列強諸国の一角に立つことを目指していった。そして日本は、そうすることで、歴史的な敗戦で荒廃しながらも、戦後は、世界第2位の経済大国に成長した。
一方のイギリスは、ヨーロッパ文明のルーツである、ギリシアやローマ文明圏の国である。言語もラテン語を基礎とし、ローマ字を今でも用い、キリスト教を受け入れる国である。かつてはローマ帝国の支配下に属州としてその身を置いた歴史を有す。他のヨーロッパ諸国がそうであるように、ローマ帝国の文明を継承している西ヨーロッパの国なのである。しかし、イングランドは長くローマ・カトリックというキリスト教圏にありながら、16世紀にはローマ・カトリックから離脱、ローマ帝国のレガシーを引き継ぐフランス、スペインなどのヨーロッパ大陸諸国とは袂を分かち、その脅威、圧迫から脱し、新興海洋国家として世界に羽ばたいていった。やがてイギリスは古代ローマ帝国をも凌ぐ、七つの海にまたがる大英帝国を築いた。戦後は多くの植民地を失い、ヨーロッパの一員に回帰してEUに加盟したが、大きな議論の末にEUを離脱し、再び「グローバル・ブリテン」を目指し動き始めた。この動きを不思議に思う人が多いが、イギリスは、EUにとどまることによる今日的なデメリットを感じる人々が多くなっていることだけでなく、我々が考える以上に、ヨーロッパ離れメンタリティーがその底流にあることに気づかされる。
両国の歴史の相違点は
とはいえ同じ島国でも、地理的、地政学的な立ち位置の微妙な違いにより、異なった国家/王朝の成立史を持っている。最も顕著な違いは「外からの征服者の存在の有無」である。
すなわち、同じ島国でも日本列島は大陸から比較的に離れていて孤立していたこと。ブリテン島のように簡単に渡れない島であった。逆に言えば、大陸の王朝や異民族からの侵攻、征服を受けにくかったと言える。大陸から列島への渡来人は、征服者ではなく亡命者、難民であった。縄文文化が1万年以上も続いたのも、この世界から「適度に」孤立した地理的環境のためであると考えられている。そのため、歴代中国王朝の帝国と地続きの周辺国(朝鮮半島、ベトナム、北方異民族の匈奴、モンゴル、女真族/満州族、西方異民族の突厥、ウイグル、チベットなど)は、中華思想/華夷思想(北狄南蛮東夷西戎)に基づく「朝貢冊封体制」に組み入れられたか、それをめぐっての長い攻防があり、時には異民族による王権簒奪、王朝交代すら起きた(万里の長城に象徴される)。しかし海を隔てた日本は、倭の時代をのぞけば、その華夷思想による東アジア的秩序の外にいた。逆に、歴代中国王朝は、基本的に大陸国家であり、周辺諸民族も中国王朝との攻防には関心が高かったが、東夷の海中にある日本列島に関心が薄かった。結果的に、日本は外敵の侵攻を恐れることもなく(元寇などいくつかの事件を除き)、列島内の、いわば同族同士の支配権力闘争に明け暮れた。支配王朝が外敵、征服者の侵攻を受けて打倒される歴史がない(中国王朝、イングランド王朝などのように)ため、「天孫族の子孫」である「万世一系の天皇」が支配する国という思想が生み出され、それが王権の歴史であるとされた(記紀の記述)。即ち中国における伝統的な「易姓革命」による王権交代という思想は取り除かれた。そこから「統治権威」と「統治権力」の二元統治制が生まれ、「統治権力」を天皇、貴族、武家が争い、奪い合っても、天皇の「統治権威」は不変とされた。対外的な脅威に対しては「鎖国」でこの秩序を守った。日本が外敵の侵攻を受け、外国の軍隊に占領されるという未曾有の大惨事にあっても、「国体護持」だけは守った。均質性と内向き、内部ロジックによる物事の決定、という伝統的思考方法が底流に厳然と貫かれた。
一方のイギリスは、ブリテン島が地理的に大陸に近く、早くから絶えずローマ帝国、アングロ・サクソン、デーン、ノルマンなどの異民族の侵攻、征服を受け続けた。ローマ帝国の属州となったのも、ヨーロッパ大陸に近い島という地理的な位置によるもの。11世紀のノルマンの征服で、ようやく異民族の侵攻に終止符を打つことができたのだが、このウィリアム1世のノルマン朝は、大陸から侵攻してきた征服王朝である。これ以降の、10王朝、41代続く英国王室の国王/女王の始祖である。一方、それ以降も絶えず大陸諸国、特にフランス、スペインの絶対王権との王位継承や領土、宗教をめぐる抗争に巻き込まれ続ける。大陸に領地を持つ王、それを抗争で失う王、ローマ法王に破門される王などがいて、封建貴族から王権が制約される(マグナカルタ)。100年戦争やばら戦争により封建領主が没落してゆくが、王権が大陸諸国に比べて弱く、身分制議会である議会制度が生まれ、力を持つこととなる。絶対王政が確立したのはヘンリー8世〜エリザベス1世の時代。英国国教会を建ててローマ・カトリックから離脱してゆく。しかしその後も議会勢力と非カトリック勢力が強く、イギリス革命により絶対君主制から議会を中心とした立憲君主制へと移行していった。英国国教会(非カトリック)+東インド会社(重商主義政策)という両輪で、ローマ帝国、ローマ・カトリックのレガシーを受け継ぐ大陸国家、絶対王権のフランスやスペインに対抗する歴史を歩む。国外情勢の変化が自国の存亡に直結するという歴史は、物事の決定は、身内の内部ロジックだけではなく、多様性を前提とした、外部環境の情報を収集、分析し、戦略的にという伝統を培った。
考察
日本にとっての中国文明、歴代中国王朝。イギリスのとってのローマ/ラテン文明、ローマ帝国/ローマ・カトリック。その受容と、そのくびきからの離脱。この緊張感が国家の成長と発展の大きな原動力になっていた点は共通すると言える。いわば、既存の、古いパラダイムから脱して、新しいパラダイムを開いていった。こうした地政学上の共通点で、ユーラシア大陸の東西両端の島国は、同じような道を歩んだと言って良いだろう。いわば、のちの時代にあっては、日本の「脱亜入欧」、イギリスの「脱欧入亜」という共通するモーメントにつながるのである。しかし、こうした動きへ突き動かす要素は何なのだろう。
まず、両国とも古代文明発祥の中心ではなく辺境であったこと。大陸から離れた島嶼国として先進文明を受容し変容させていった歴史を持つこと。その先進文明と強大な帝国の影響を受けつつも、その支配下に置かれるという桎梏と圧迫から脱しようとするモチベーションが常にあったこと。島国であり、広大な領土を有する大陸国家ではなかったことから、国力/経済力発展の源泉を海外に求めざるを得なかったこと。土地と資源のない貧しい国として、貿易拡大、科学技術の発展、産業革命と海外植民地拡大により国力をつけていったこと。日本は鎖国でイギリスに遅れること200余年で、そのムーヴメントにキャチアップして行こうとしたので時差があるが、こうした要素が根底にあるのではないか。
ただ既述のように、国家/王朝の成立事情には違いがある。イギリスは、大陸からの征服者の侵入が繰り返され、9世紀にアングロサクソンの統一王国、11世紀になって、フランスからやってきたノルマン王朝成立で、ようやくイングランド王国の基礎が固まった。しかし、以降も、周辺国との緊張関係と、生き残りへの危機感は、それに対応する対外戦略(外交と、最後は戦争という)を持つ必要に迫られた。日本は、5世紀頃、倭国に初期ヤマト王権が、7世紀に天皇制、律令制国家として日本(ひのもと)が成立した。王権の成立という点では日本が早かったといえよう。これは、外敵の侵入による征服、王権の簒奪がなかったことによると考えられる。17世紀の西欧勢力/キリスト教の来航に際しては「鎖国」で国を守った。いや「鎖国」しても誰も攻めて来ない幸運な外部環境だったとも言える。いずれにせよ、その結果、封建領主制度が19世紀半ばまで続き、19世紀の欧米列強の来航をきっかけについに開国し、封建制が崩壊した。「王政復古」(絶対王政から立憲君主制へ)という近代化革命を断行して危機を乗り切ろうとした。こうした歴史が、イギリスと異なり日本という国が、内政中心で対外戦争や外交に弱い原因の一つになっているとも思慮する。
21世紀の超大国は、ややピークが過ぎたアメリカと、中国そしてインド。いずれも大陸国家である。しかも海外進出に積極的に挑む大陸国家である。しばらくは三つ巴の覇権争いになるであろう。中国とインドは、長らく「古い文明の象徴」、「西欧列強の植民地」、「近代化に出遅れた新興国」という地位に甘んじてきたが、急速に経済成長し、人口も10億を超える大国である。それとともに軍事大国化も急であり、それが周辺国の脅威となっている。日本やイギリスのような大陸周辺に位置する島国が、経済大国に発展し繁栄した歴史は過去のものなのか? 過去の先進文明、巨大帝国からのサバイバル経験は生きるのか? 特に日本は、これまでのように、海で隔絶された島国、海洋進出に関心の薄い大陸国家が隣人、という「利点」をもはや享受できるわけではない。人、物、金、情報が自由に行き来するフラット化したボーダレスな空間の中で、強力な競争相手とやり合ってゆかねばならない。絶えず異質で多様な価値観に晒され、これを受容し、あるいは戦ってゆかねばならない。いわば「海に隔てられた囲まれ感」のない世界を生きてゆくことになる。また「追いつけ、追い越せ」で必死に走ってきたが、気がつくと「追いつかれ、追い越され」てしまった時の、次のゲーム・プランへのシフトができないまま30年思考停止している。同じ島国として栄枯盛衰を経験してきた、強かなイギリスは、日本がバブルで浮かれていた時には、「英国病」だ「「老大国」だ揶揄されて、ああなってはならない、の見本のように言われていた。日本人はイギリスに対して傲慢に見下していた時期すらある。しかしその後のイギリスの復活のプロセスへの評価と、それへの学びの姿勢は日本にはない。イギリスはその世界に冠たる繁栄の時代が200年続いた。日本の経済大国「ジャパン・アズ・ナンバーワン」の時代はせいぜい30年。歴史に対する俯瞰的な視点と、未来を予測する想像力(下記、17世紀のウォルター・ローリーの論考を参照)を涵養する間もなく停頓の時代に突入してしまった。今こそ、イギリスの世界観、歴史観と、サバイバル戦略、外交戦略の歴史から学ぶことは多いだろう。戦後、アメリカばかり見てきた視点を少し変える必要がある。
参考(1): サー・ウォルター・ローリー「エッセイ集」「戦争論」1650年より引用
「ブリテンがローマ帝国に勝利して以降、聖職者は全てイングランド国王に臣従してきたし、ローマ法王が、イングランドにおいて、内政問題であれ、聖職者の活動であれ、いかなる法的な権力を有したことは一度もない」(翻訳引用)
「海を制するものは交易を制す。交易を制するものは世界の富を制す。すなわち世界を制す」。17世紀のエリザベス1世の寵臣にして、冒険的航海者、歴史家、著作家であるウォルター・ローリーの言葉である。彼はこの論考集の中で、反ローマ・カトリック、反スペインの姿勢を明確に論述し、やむを得ない戦争(大義ある戦争)と侵略を目的とした戦争(大義なき戦争)とを区別した戦争論を展開している。ローマ・カトリックをいわば「古いヨーロッパの(ローマ帝国のレガシー、系譜に連なる)価値観と思想の代表」と捉え、イングランドがやがて古い秩序と価値観を打ち破り、「古代ローマ帝国に代わる世界帝国としての繁栄と栄光を獲得する」という未来を予言する論説となっている。そのためにはスペインやフランスとの融和ではなく「大義ある戦争」に備えなければならない、と。このイングランドの未来を予見し、方向を指し示したこの論文が17世紀の初頭に発表されていることに注目したい。
2022年9月12日「古書をめぐる旅(25)サー・ウォルター・ローリー エッセイ集」
参考(2):日英両国の成り立ち(古代〜近世)
日本
大陸からの中国文明の流入
古代中国王朝にとっては「東夷」の海中の「倭」
原住民 原日本列島人(縄文人)
紀元前10世紀〜 弥生時代の始まり 大陸から稲作と青銅器、鉄器の流入 縄文時代から弥生時代への転換 大陸からの渡来人と原日本人(縄文人)との混血
1世紀〜3世紀 中国王朝の朝貢/冊封体制のもとで「倭」国を統治 中華文明の影響下に。
57年 倭奴国王 後漢の光武帝に朝貢、冊封
107年 倭国王帥升等 後漢に朝貢、冊封
239年 倭邪馬台国女王卑弥呼 魏の明帝に朝貢、冊封
266年 倭邪馬台国女王壹与 晋に朝貢、冊封 以降、147年中国への朝貢の記録なし
413年〜502年 倭の五王 中国王朝に遣使、朝貢 朝鮮半島支配権の冊封を乞う
3世紀〜6世紀(古墳時代) 大陸は、漢王朝の滅亡、三国分裂、五胡十六国時代へ 統一王朝がない混乱の時代 大量の渡来人が来島(難民、亡命漢人) 倭国は、初期ヤマト王権の成立 中国の朝貢冊封体制から徐々に離脱 朝鮮半島との関係が強まる
369年 朝鮮半島三国の対立 百済の要請で朝鮮半島へ出兵
391年 百済、新羅を破る(好太王碑文)
404年 高句麗と戦闘 倭軍撤退
538年/552年 百済の聖王より仏教伝来
589年 中国に統一王朝「隋」の誕生、
618年 これを引き継ぐ「唐」の成立と繁栄の時代へ
607年、614年 遣隋使(朝貢使とは異なる扱い)
630年 遣唐使開始(朝貢使とは異なる扱い)9世紀初頭まで続く
645年 「乙巳の変」 大王権力の集中との強化に向けた大化の改新の始まり
663年 朝鮮半島利権をめぐって出兵 「白村江の戦い」で、唐・新羅連合軍に敗北 朝鮮半島からの撤退 列島への侵攻の危機
これを機に、倭国の国家体制、軍事体制の建て直し 中国王朝の制度を取り入れて「近代化」=「大宝維新」、天皇制、律令制 公地公民制、仏教による鎮護国家思想、正史の編纂よる独立国家アイデンティティー、中国王朝の朝貢冊封体制からの離脱完成 倭国から日本(ひのもと)へ
平安時代 貴族中心の摂関政治 律令制の変容 遣唐使がなくなり国風文化 一種の内向き志向の原型
鎌倉時代 武家政権誕生 元寇があり、初めて日本列島に外国勢力が侵攻してきた
室町時代 武家政権 海外進出を企図する 勘合貿易 しかし幕府の統治権力弱体化/群雄割拠の戦国時代へ キリスト教伝来 西欧文明とのファースト・エンカウンターの時代
江戸時代 武家政権の安定期 戦国内乱の時代の終息を経て、大航海時代に海外進出、海外との交易拡大を企図するも、キリスト教受容を拒否し鎖国 200年余り内向き志向
1854〜1867年の開国、明治維新 封建領主制(幕藩体制)の解体 武家支配の打倒「王政復古」 西欧流近代化(文明開花、殖産興業、富国強兵)、 中華体制/華夷思想を前近代のものとして否定(脱亜入欧)西欧列強と植民地獲得競争に参入するもやがてその競争に負けて敗戦、戦後はアメリカの庇護の下復興し、経済大国に
イギリス
大陸からのローマ文明/キリスト教の流入
原住民 ケルト族系ブリトン人
43年 ローマ帝国のブリタニア属州に
122年 北方のケルト人の侵入を阻むハドリアヌスウォール構築
375年 ゲルマン民族の大移動開始 ローマ帝国崩壊の兆し
395年、ローマ帝国の東西分裂、
409年 ローマ帝国、ブリタニアから撤退
449年、ゲルマン系アングロ・サクソンのブリタニア侵入 以降、絶えず大陸から異民族の侵入を受ける
476年 西ローマ帝国の滅亡 東ローマ帝国はビザンツ帝国へ(ギリシア正教)
489年 フランク王国成立(ローマ・カトリック教会、ローマ帝国のレガシーを引き継ぐ) のちのフランス、スペイン、ドイツ(のちには神聖ローマ帝国)
7世紀、イングランド7王国時代 アングロ・サクソンの王国が成立
768年〜814年 フランク王国シャルル大帝(ピピンの子) ローマ帝国、ローマ・カトリックのレガシー継承
9世紀、ノルマン(バイキング)の活躍、(ブリタニア、アイスランド、グリーンランド発見)
827年、ウェセックス王エグベルト、イングランド統一 イングランド王国成立
871〜901年、ウェセックス王アルフレッド大王の治世 アングロ・サクソンの王国
1001〜1004年、ノルマン人のイングランド侵攻
1016年〜1042年 デーン人によるイングランド支配 アングロ・サクソン王国と対立
1066年、「ノルマンの征服」 フランスのノルマンディー地方の貴族、ノルマンディー公ウィリアムがブリテン島に侵攻 へースティングの戦いでアングロ・サクソンのハロルド王を破りイングランド王ウィリアム1世として即位。征服王朝ノルマン王朝成立 強力な王権を確立し、以降大陸からの侵攻がなくなる フランス語の国王 フランスにも領土を持つ。
ノルマン朝は、現代まで続くイギリス王室の始祖とされ、以降10王朝、41人の国王、女王に継承される。ケルト・ブリトン文化、ローマ文化、アングロ・サクソン文化、ノルマン文化、フランス文化が重層的に重なり合った独特のイングランド王国の誕生
中世は、西ローマ帝国、フランク王国の系譜を継ぐ、ヨーロッパ大陸のスペイン/フランス王権の隆盛、ドイツは神聖ローマ帝国皇帝を継承 ローマ・カトリックの権威、ローマ教皇の権力が強大 弱小島嶼国イングランドの苦闘
16世紀末 ヘンリー8世による宗教改革(英国教会設立)、ローマ・カトリック(ローマ帝国のレガシー)からの離脱 一方でピューリタンなど非国教会プロテスタントの抵抗もあり弾圧、北米へ脱出する(ピルグリムファーザーズ)
17世紀 エリザベス1世の絶対君主制 スペイン。フランスの勢力圏から脱して海外へ(スペイン無敵艦隊を撃滅) 反カトリック、重商主義 その後、イギリス革命を経て立憲君主制国家へ イギリス繁栄の基礎
18世紀以降、産業革命、インド支配など世界に海外植民地拡大で繁栄する海洋国家へ ローマ帝国を凌ぐ大英帝国へ
19世紀 大英帝国繁栄 パクス・ブリタニカの時代
二つの世界大戦に勝利するも、戦後は植民地を失い国力衰退、ヨーロッパ回帰(EU加盟) しかしEU離脱 再び「グローバル・ブリテン」復活へと舵をきる